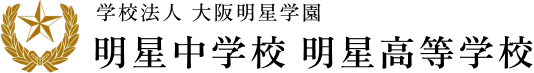文化財技師、という仕事をご存知でしょうか。
わたくしは、京都府庁で美術工芸品担当の文化財技師として仕事をしています。
文化財には、建造物・美術工芸品などの有形文化財のほか、無形文化財・民俗文化財・史跡名勝天然記念物・伝統的建造物群保存地区・文化的景観など、実に多様なものが含まれます。このうち、美術工芸品には「絵画」「彫刻」「工芸品」「書跡・典籍」「古文書」「歴史資料」「考古資料」という、これまた多様なものが含まれます。わたくしは大学時代に文学部の美学美術史研究室で仏像について研究していました。今は仏像をはじめとした「彫刻」や「工芸品」などの保護に関する仕事をさせていただいています。
文化財行政には、大きく「指定」「制限」「補助」の3つの柱があります。世の中に無限に存在する文化財の中から、調査を行って特に価値の高いものを「指定」します。無事指定された文化財には、所有者・所在場所の変更、公開、毀損や修理に対して許可や届出を課すなど、その価値が保たれるよう、一定の「制限」がかけられます。その代わりに、修理や防犯対策など、その価値を保つために行われる行為には「補助」の仕組みがあります。
これらを通して価値の高い文化財を後世に継承する手助けをするのが我々の仕事です。傷んだ絵画や仏像、穴の開いた古文書などを前にして、その文化財の所有者と、国指定文化財であれば文化庁、その場所の市町村の担当者、修理技術者との間を繋ぎ、文化財が少しでも良い状態で次の世代につなげられるように奔走する調整役、と言えると思います。
仏像に興味を持つきっかけは、明星在学中だった気がします。在学中は美術部に所属し、近所の古社寺を風景画に描いて学園祭で展示したりしていました。また、高校の美術の授業で「自由なテーマで本を一冊仕上げる」という課題があり、そこで「河内西国三十三か所」という、西国巡礼のローカル版霊場があるのですが、近所なのでそれを順番に回って絵に描いて一冊にまとめたこともありました。そうした機会にお堂の中に祀られる美しい仏像に興味を持ちました。もともと日本史は好きでしたし、仏像が作られた時代背景にも興味がわき、大学で日本彫刻史のゼミに入りました。中学高校時代に興味を持った日本の仏像に関わる仕事を、今もそのままさせていただいているのは、幸せなことだと思っています。
文化財技師は、たくさんの文化財を間近に見られ、著名な専門家、修理のプロなど、多くの方々から直接学ぶ機会が得られる、とてもやりがいのある仕事だと実感します。今後お寺や神社、美術館などで美術工芸品を見たときには、その背後で、それをどのようにして後世に守り伝えるかに心を砕いているわたくしたちがいることに、思いをはせていただけると嬉しいです。また、文化財を取り巻く仕事には、私たち文化財技師のほかにも、博物館の学芸員や、各分野の文化財修理技術者など、さまざまあります。日本史が好きな方や、仏画や襖絵、仏像、陶器や刀剣などの工芸品などに関心がある方などには、文化財に関わる仕事という進路もある、ということを知っていただければと思います。