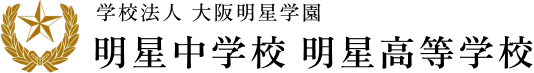地歴部
まず顧問の先生方の紹介です。加島先生・木村能幸先生・須澤先生・違口先生・今村先生の五人の先生がいらっしゃいます。担当教科も社会科の先生ばかりでなく、英語科・家庭科・国語科の先生とバラエティーに富んでおります。
次に活動内容の紹介に移りましょう。金曜日の集まり以外には、須澤先生がティームス上で、各自の研究課題・テーマに関して意見交換をする場を設けております。
そして金曜日は、加島先生の担当です。この日は、江戸時代に活躍した学者である頼山陽先生の著書『日本外史』の講読をしています。『日本外史』とは、平安時代末期から江戸時代までの武士の時代の歴史絵巻を活写した血湧き肉躍る歴史書です。幕末維新の頃は、志士たちの誰もがこの書物を読んでいました。漢文書き下し文の原文は読むのも理解するのもとても難しいですが、加島先生が丁寧に解説してくれますので、内容はちゃんと理解できて楽しめようになっていますよ。
これまでに読んだのは、神戸でのフィールドワーク(湊川神社等見学)に関連して、楠木正成公の「湊川の戦い」の場面。大河ドラマ『真田丸』放映の年は、「大阪の陣」の場面。(明星学園は、真田丸のあった場所に位置していると言われています)。昨年度は、アニメ化もされました『逃げ上手の若君』にちなんで、鎌倉時代末期から南北朝時代・室町時代初期の部分を扱いました。今年も継続して読みます。どうかお楽しみに。
また三年前が森鴎外没後百年の年でしたので、森鴎外の歴史小説の講読もしております。江戸時代にここ大坂で起こった大事件『大塩平八郎の乱』を扱った『大塩平八郎』という小説も併せて講読しております。
さらに昨年度にはアメリカ大統領選挙もありました。世界の超大国アメリカ合衆国をよりよく理解するために、現代のアメリカの形を作ったと言われる「南北戦争」について詳細に論じています。
また週末などに各地の美術館・博物館で歴史を扱った展示の見学会や、長期の休暇を利用してフィールドワーク等を行っています。昨年度の実施した内容は、雑誌明星のクラブ紹介欄に掲載されていますのでご覧ください。年に一度合宿を行うこともあります。学校の近所にある大槻能楽堂で年二回催される「中高生のための能楽鑑賞」にも参加しています。
能楽は、扱う題材が歴史上の事件や出来事なので地歴部と相性がいいですし、能の台本をあらかじめ読んで歴史背景をしっかり押さえておいてから作品を鑑賞しております。ですから能楽でも決して敷居が高いということはありません。これまでに『敦盛』や『俊寛』、『安達ヶ原』などを見ました。昨年度は『小袖曽我』と『葵の上』を鑑賞いたしました。
フィールドワークで、美術館や博物館を訪れる前には必ず事前学習を施しています。ですから現地で何も分からなくて退屈で困ってしまうということは決してありません。
本や文献史料からだけでなく、実際に現地に足を運び、自分の目で見てその土地の歴史や地理(鉄道も含む)を学び感じることも地歴部では重視しております。毎年部員一同で決めたテーマを協力して調べて疑問点を発見し、文献や現地を調べ、そこから導き出される仮説に裏付けを加えた新説を学園祭で展示し、機関誌『史疑』で詳しく発表しています。
研究成果は、奈良大学主催の「歴史フォーラム」というコンテストにエントリーしています。この「歴史フォーラム」に入賞することは、地歴部の長年の悲願となっています。みなさんが地歴部に入部して、この宿願の達成のための新たなる力となって欲しいと思っています。
この部としての全体のテーマの他に、各部員それぞれの研究課題・テーマを持ってもらうようにしています。そして適時、研究成果を部員みんなの前で発表して、プレゼンテーションをしてもらいます。そして各顧問の先生方による論文審査も行います。そしてその成果は、機関誌『史疑』に掲載して公表いたします。
また戎光祥出版株式会社という出版社が発行している雑誌『歴史研究』が「学生招待席」というコーナーを設けております。ここに中学・高校生などが書いた歴史に関する論文を投稿し、優秀なものは紙面に載せてくれています。これに応募することを考えています。あるいはまた、「歴史検定」という検定試験にも積極的に参加していこうとも考えています。
みなさんも興味関心のあることを研究・調査してそれを論文にまとめて発表してみませんか?自分の考えをそのようにまとめて公にして、周囲からのフィードバックを受けてさらに考察を深めるという経験は、スリリングなものですし、このようなプロセスがこれからの世の中ではとても大事になると思います。
以上、地歴部の活動を紹介してきました。大学で学ぶことにも匹敵するくらいの高度な内容を扱っていると思います。大切なことは、自分で疑問点・課題を見つけて、それを調査・研究し、問題点に対する自分なりの答えを見つけて、それを検証・立証するだけの証拠集め・証拠固めを行い、さらにそれを論文の形にまとめて、みんなの前でプレゼンができるようにすることです。そして周囲からの反応をもとにさらに考察を進めていく。
これは大学での研究、さらには就職して社会に出た後にも絶対必要とされる能力でもあり、新しい学習指導要領にも沿った活動になります。このような大人になってから必要となるスキルを、今からこの地歴部で一緒に習得していきませんか?事実、過去の地歴部卒業生たちの中には、難関大学へと合格している人も多数います。昨年度の卒業生は全員現役で難関大学へ進学しています。皆さんの地歴部への入部・参加を、首を長くして待っております。意欲のある人大歓迎!来たれ、中高生!
今年予定しているフィールドワークの内容です。
○大阪城天守閣にて『大坂城再築』
○開館記念『大阪城豊臣石垣館』
○大阪歴史博物館にて『日本刀1000年の軌跡 名刀を超えろ』
○奈良国立博物館にて『超国宝展』
○京都国立博物館にて『日本、美のるつぼ展』
○大阪市立美術館にて『日本国宝展』
○京都文化博物館にて『和食展』
○神戸市立博物館にて『蒐集家・池長孟の南蛮美術展』
○龍谷ミュージアムにて『大谷探検隊吉川小一郎展』
○大阪くらしの今昔館にて『大坂から大阪 住まいのかたち展』
○京都国立博物館にて『宋元仏画展』
今年度、金曜日の集まりで扱うテーマの一覧です。
★鎌倉時代末期から室町時代初期までの日本史の大転換期を見ていきます。
★三年前は森鴎外没後100年。それにちなんで、森鴎外の作品『大塩平八郎』を講読します。
★それの理解のために、大塩中斎先生(大塩平八郎先生)が、困窮せる民衆を救うという大義のために立ちあがった義挙
(俗に「大塩平八郎の乱」と呼ばれているもの)の際にばらまいた檄文を原文で読んでみます。
★アメリカ南北戦争について、その詳細を追う。